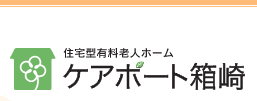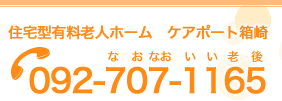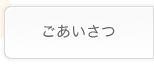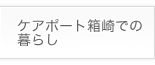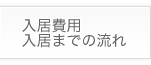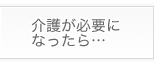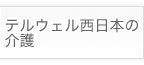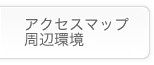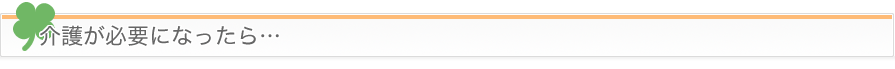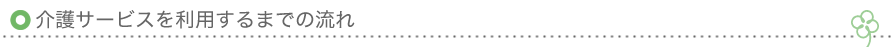| トップページ > 介護が必要になったら… |
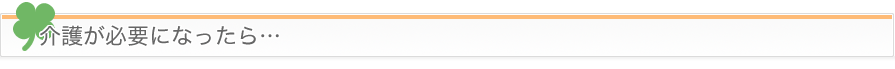 |
| |
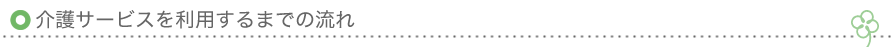 |
【ご注意】
このページの内容は、介護サービスを利用するまでの大まかな流れを理解していただくために、『福岡市の介護保険制度』から引用して構成したものとなります。より詳しい情報や最新の情報は、上記ホームページにてご確認下さい。 |
|
|
| |
 |
介護サービス・介護予防サービスを利用する人は、住所地の区の保健福祉センター福祉・介護保険課か、今宿・入部出張所で要介護認定の申請をしてください。
認定の申請は、家族などが代理で行うことができます。また、寝たきりの家族の介護などで申請に行くことができない場合などには、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、介護保険施設に申請を代行してもらうこともできます。 |
|
 |
 |
介護サービス・介護予防サービスを利用できる人
●第1号被保険者(65歳以上の人)
原因を問わず、日常生活を送るために介護や支援が必要な人
●第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)
老化に伴う病気(特定疾病)が原因で、日常生活を送るために介護や支援が必要な人
申請に必要なもの
●要介護認定・要支援認定申請書(区保健福祉センターの窓口にあります)
●介護保険被保険者証
●40歳以上65歳未満の人は医療保険被保険者証 |
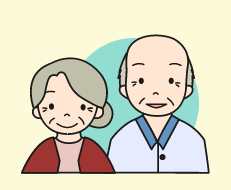 |
|
 |
 |
|
| |
 |
| 各区保健福祉センターの職員や調査の委託を受けた事業者などの介護支援専門員が、事前に日程を確認のうえ、自宅などを訪問し、心身の状況の調査を行います。 公平な判定を行うため、訪問調査の結果はコンピュータを用いて一次判定を行います。 |
|
| |
 |
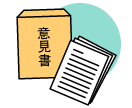 |
市が本人の主治医に、心身の状況についての意見書を作成してもらいます。 |
|
| |
 |
訪問調査の結果と主治医意見書をもとに「福岡市介護認定審査会」で、介護の必要性や程度について審査を行います(二次判定)。
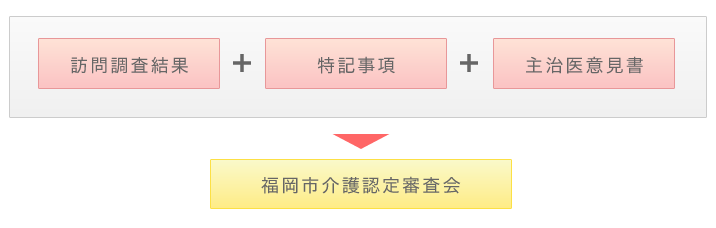
 |
 |
福岡市介護認定審査会とは?
「福岡市介護認定審査会」は、保健・医療・福祉の学識経験者で構成され、介護の必要性や程度について審査・判定を行います。 |
|
 |
 |
|
|
| |
 |
介護認定審査会の結果にもとづいて「非該当」、「要支援1・2」、「要介護1〜5」までの区分に分けて認定し、その結果を通知します。
|
|
| |
 |
認定結果をもとに、心身の状況等に応じてケアプランを作成します。
 |
 |
要支援1・2、非該当と認定された人
介護予防ケアプランを作成します。地域包括支援センターが中心となって介護予防マネジメントを行います。要支援1・2または非該当と認定された人は、介護保険の介護予防サービスまたは福岡市が行う地域支援事業の介護予防事業を利用することになります。
要介護1〜5と認定された人
ケアプランを作成します。認定結果をもとに居宅介護支援事業者に依頼し、介護支援専門員(ケアマネジャー)に心身の状況に合ったケアプランを作成してもらいます。
ケアプランの作成を依頼する事業者が決まったら住所地の区保健福祉センター福祉・介護保険課へ「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出します。
※ケアプランの作成は無料です。
|
|
 |
 |
|
|
| |
 |
 |
ケアプランにもとづいて、在宅や施設でサービスを利用します。サービスを利用する人は、原則サービス費用の1割をサービス事業者に支払います。日常生活に要する費用(食費、居住費(滞在費)、宿泊費、日用品費など)については、自己負担となります。 |
|
| |
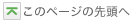 |
| |